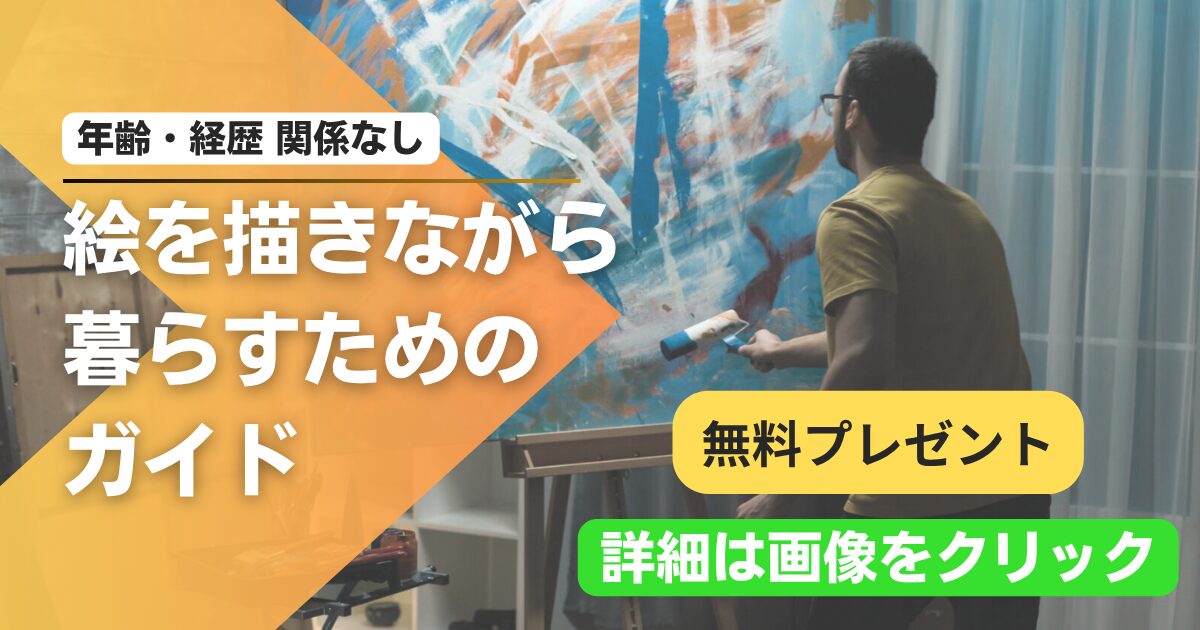※当サイトはページ内に商品プロモーションを含む場合があります。
クレヨン・パステル・クレパスの違いとは?特徴や保存方法も紹介

- クレヨン・パステル・クレパスの違いが知りたい
- クレパスで本格的な絵が描けるか知りたい
- クレヨンは画材として使えるのか知りたい
上記のようなお悩みについてお答えします。
クレヨン・パステル・クレパスは見た目が似ていますが、それぞれ特徴が異なります。
小学校などで使ったことがある人も多いと思いますが、学童用の画材というわけではありません。
プロの画家が本格的に絵を描く際にも使われる画材です。
そこで今回は、クレヨン・パステル・クレパスの違いや特徴についてわかりやすく解説します。
本記事を読むことでクレヨン・パステル・クレパスについて理解を深め、アート制作に活かせます。
クレヨン・パステル・クレパスの違いと特徴
クレヨン・パステル・クレパスは一見すると同じ画材に思えますが、別の画材です。
こちらでは、それぞれの違いと特徴について紹介します。
クレヨン
クレヨンは顔料をロウなどの固形ワックスで固めたものです。
硬さがあり、紙に定着しやすいのが特徴です。
はっきりとした線を描くのに向いていますが、紙の上で混色することはできません。
海外では硬いタイプが主流ですが、日本では液体油などを混ぜて、よりなめらかになっているタイプもあります。
パステル
パステルは、粉末にした顔料を粘着剤で固めたものです。
粉末状にして塗り広げたり、画面上で色を混ぜ合わせたりして使えるのが特徴です。
発色がよく色数も豊富で、ふんわりとした色彩豊かな表現に適しています。
定着が弱く粉落ちしやすいため、描いた後はフィキサチーフなどの定着材を使って保護する必要があります。
また、パステルにはソフトパステルやハードパステルなど、種類があるのも特徴です。
クレパス
クレパスは、クレヨンとパステルの長所をあわせ持った画材です。
日本のサクラクレパスが開発し、クレヨンの「クレ」とパステルの「パス」をとって命名されました。
クレパスは商品名で、画材としては「オイルパステル」になります。
クレヨンよりもやわらかく画面上で混色でき、ぼかしや重ね塗りなど幅広い表現が可能です。
本格的な制作に使う場合は、専門家向けの顔料が使われている「クレパス スペシャリスト」がおすすめです。
クレヨン・パステル・クレパスの描画の違いを押さえておこう
クレヨン・パステル・クレヨンの描画の特徴を押さえて、表現方法にあった画材を選びましょう。
| 描画 | クレヨン | パステル | クレパス |
|---|---|---|---|
| 線画 | |||
| 面画 | |||
| 混色 | |||
| 塗り重ね |
描いたあとはそれぞれに適した保護剤を使って作品を保存しよう
描いたあとそのままにしておくと画面が崩れたり、色移りしたりしてしまいます。
完成後は、画材に適した保護剤を使って表面をコーティングしましょう。
また、保存する際は直接触れないように額装しておくのがおすすめです。
パステルの仕上げ
パステルは定着が非常に弱いため、定着材の「フィキサチーフ」を使います。
フィキサチーフは鉛筆画などにも使われるため、パステル用を選ぶとよいでしょう。
また、描いている途中で今の状態を定着させてから、さらに描き進めることも可能です。
クレヨン・クレパスの仕上げ
クレヨンやクレパスは定着力が強いですが、直接触ると色移りしやすい性質があります。
そのため、クレヨンやオイルパステルに使える保護剤を塗布します。
1度の塗布では保護しきれないことがあるため、複数回使うのがポイントです。
また、サクラクレパスには仕上げ用の保護剤の他に、描いている途中で下の色と混ざらないようにする重色用もあります。
まとめ|クレヨン・パステル・クレパスの特徴を活かして制作しよう
本記事では、クレヨン・パステル・クレパスの違いや特徴などについて紹介しました。
それぞれの異なる特徴をしっかり押さえることで、表現の幅を広げることに役立ちます。
また、描いたあとに画面が崩れたりしないよう、適した保護剤を使って作品を保存しましょう。
また、クレパスなどのオイルパステルについて、以下の記事で詳しくまとめています。

最後まで読んでいただきましてありがとうございます。
-
URLをコピーしました!